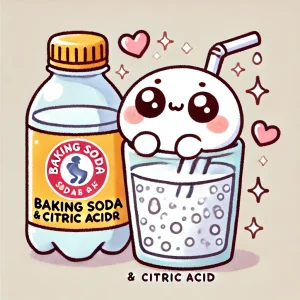インターネット上で重曹クエン酸水が体に良いと知って、自分なりに調べてから飲み始めて2年半以上が経過しました。太りづらくなったこと以外はあまり実感ないのですが、55歳の現在でも健康診断で問題になることはなく、体調を大きく崩すこともないので健康維持に役立っているのではないかと思っています。
なぜ? 重曹クエン酸水(重曹とクエン酸を混ぜた水)かと申しますと、体内のpHバランスの調整によるアルカリ化に注目しています。特に細胞間質液(組織液)のアルカリ化で癌や糖尿病の症状が改善されるという情報が興味深いものでした。
飲み始めるにあたって調べたメリットとデメリット。
メリット
-
pHバランスの調整:重曹はアルカリ性、クエン酸は酸性ですが摂取すると体内でアルカリ性に変わります。体内の酸性度(pH)を中和する働きがあります。細胞間質液が、ややアルカリ性であると、細胞の代謝が促進され、酸性に偏りがちな環境を整えることで細胞機能の改善が期待できます。
-
消化のサポート:重曹とクエン酸が混ざると反応して炭酸ガスが発生します。このガスによって飲み物が発泡し、飲むと胃に軽い刺激を与えることがあります。この炭酸ガスが胃をやさしく刺激し、胃腸の運動を促進することで、消化をサポートする可能性があります。また、クエン酸は胃酸の分泌を助け、消化をサポートします。これにより、胃の働きが活発になり、消化不良の改善に役立つことがあります。
-
疲労回復効果:重曹とクエン酸は乳酸という酸性物質の分解を助けるため、運動後や疲労がたまったときに飲むと、疲労回復が期待できます。
-
抗酸化作用:クエン酸は抗酸化物質を生成しやすい環境を作るため、酸化ストレスを軽減する効果があると考えられています。
デメリット
-
過剰摂取によるリスク:過剰なアルカリ化は逆に胃酸のバランスを乱し、消化不良を引き起こす場合があります。特に胃酸の過剰中和は、消化酵素の活性低下を招く可能性もあります。
-
腎臓への負担:重曹にはナトリウムが含まれており、腎臓に負担がかかる可能性があります。特に腎機能が低下している場合や、高血圧の方は、ナトリウム過剰に注意が必要です。
-
細胞環境への影響:アルカリ性が強すぎると細胞間質液だけでなく、血液のpHにも影響を及ぼす可能性があるため、バランスが崩れるリスクも考慮が必要です。
癌や糖尿病に対しての効果は
細胞間質液の酸性化は、癌や糖尿病の進行に影響を与える可能性があると考えられており、 癌細胞は酸性環境で増殖しやすくアルカリ環境では増殖がしづらいという報告があります。また、酸性環境はインスリン抵抗性を高め、糖尿病の症状を悪化させるという報告があります。それなら食事や生活習慣でアルカリ化にすればよいという考えになりますが、体液(血液や細胞間質液)のpHは、腎臓や肺の機能によって厳密に調整されており、食事や生活習慣だけで急激に変わることは難しいと言われています。
しかし、個人的見解で申しますと重曹クエン酸水には細胞間質液のpHバランスを改善する可能性があると感じています。それは重曹とクエン酸を混ぜた水は、単体で利用するより体内でアルカリ性の持続時間が長いという報告があるからです。通常の食事やアルカリ性の食事では長時間のアルカリ性を保つことは難しいものです。実験的に何度か自分の体の尿pHを計測しましたが7.0以上であり、摂取後20時間以上経過しても同様でした。通常は腎臓や肺の機能によってpHが調整されており尿のpHは6.0ぐらいの酸性です。尿のpHが7.0以上ということは体の中の体液がアルカリに傾いていて、尿で余計なアルカリな体液を放出していると考えることができます。このことから癌や糖尿病の症状に変化を与えることができると信じるようになりました。また、癌細胞がブドウ糖をエネルギー源にする性質を持っているため、少量のはちみつを加えることで癌に届きやすくなり、重曹クエン酸水がより効果的に届く可能性があります。一部の医師は重曹クエン酸水を推奨しておりますし、抗がん剤と併用することで抗がん剤の効果が上がるという報告もあります。
ただし、癌にはさまざまな種類があり、それぞれの進行度や性質も異なります。重曹クエン酸水だけで癌が消えたという医学的な報告も見たこと聞いたことありません。 そのため、重曹クエン酸水に過度な期待をすることは避けるべきだと思っています。 また、糖尿病を含む病状においては、pH管理それだけでなく、食生活や生活習慣の全般的な改善が必要だと思っています。
もし、試してみたい場合には、過度な摂取量に注意する必要があります。また、重曹やクエン酸は信頼できる品質のものを選び、安全性に配慮することも忘れないようにしてください。
ちなみに参考として私が摂取している重曹とクエン酸を紹介しておきます。比較的安全だと思われるものをAmazonで購入しています。分量は重曹を小さじ1/2を1杯とクエン酸を小さじ1/2の半分を100mlの水に混ぜます。少し酸味と塩気のある微炭酸水ができあがるので、それを1日1回空腹時に飲んでいます。
追記
重曹クエン酸水を飲み続けても血糖値やヘモグロビンA1c(HbA1c)が下がらない人がおります。そのような人は血液検査で調べるCRP(C反応性蛋白)の数値が高いことがあります。CRPは体内の炎症の指標であり、体内に炎症があると血糖値を上げる原因になるものだと言われています。細菌やウイルスに感染しても体内に炎症が起きます。関節の腫れや歯周病も炎症になります。また肥満や生活習慣などの影響によっても慢性微小炎症が起きます。
重曹クエン酸水を飲んでも血糖値やHbA1cが下がらない方は炎症を疑い、炎症が存在するのであれば対処する必要があります。
それと体内に炎症があったら重曹クエン酸水を摂取しても無意味なのかと言えば、そうは思いません。そのような方でも摂取していないときより摂取しているときの方が比較的元気に過ごされていると感じています。